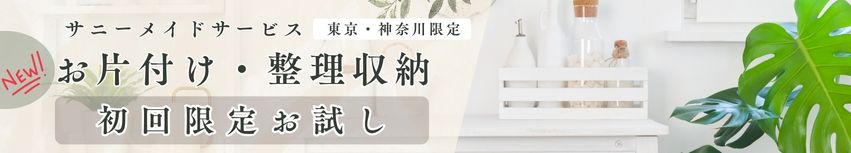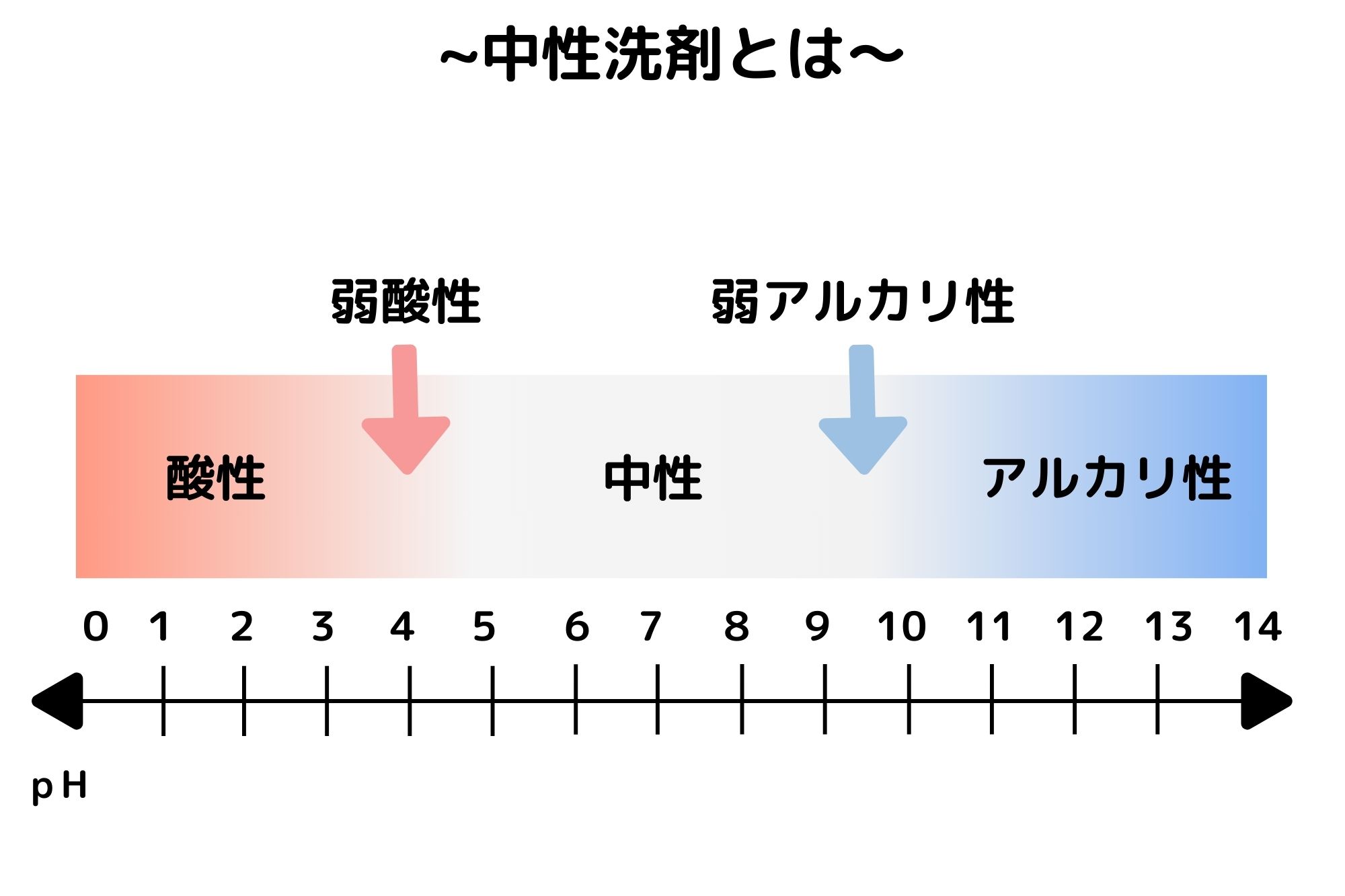COLUMN
コラム
片付けが苦手でも大丈夫!今日から始める簡単整理収納術
2025.01.29
物を捨てるのが苦手、片付け方が分からない…そんなあなたは、もしかしたら片付けが苦手かもしれません。この記事では、片付けが苦手な人の心理や具体的な原因を解説します。さらに、誰でも実践できる簡単な片付け方法や、キレイを保つためのコツもご紹介します。
片付けが苦手な人の特徴

家の中を片付けたくても、なかなか綺麗にならない…そんな方はいらっしゃいませんか。ここでは、片付けが苦手な人の特徴を紹介します。
もったいないと感じてしまう
片付けが苦手な人に共通する特徴として、「もったいない」と感じてしまい物を捨てられないという傾向があります。例えば、まだ使えるけれど使う予定がないものや、購入したけれど一度も使っていないものを手放すのが難しいと感じる方が多いです。このように物を処分する基準が曖昧だと、部屋に物が溜まり、整理収納が進まなくなってしまいます。
ものを収集するのが好き
ものを集めるのが好きな人も片付けが苦手になりやすい傾向があります。コレクションすること自体は楽しいですが、保管方法を適切に工夫しないと物が散乱し、結果的に片付ける作業が追いつかなくなります。特に、本や雑貨などカテゴリーが多岐にわたる場合は、管理が難しく感じられることが多いです。
家の中のものを把握していない
持ち物を把握できていない状態では、「どこに何があるか」が分からず、不要なものが溜まってしまいます。買い物に行った際、既に持っているものを重複して購入してしまうこともあります。このような状況が続くと、整理収納の手間が倍増し、ストレスにも繋がりやすいです。
衝動買いしてしまう
衝動買いをしてしまう人も片付けが苦手になりやすい特徴を持っています。衝動的に購入したものは収納場所を考えずに増えていくため、部屋が散らかる一因となります。また、購入した際には満足感があっても、使わないまま放置されることも多く、家の中に不要な物がどんどん積み重なってしまいます。
発達障害などの病気
片付けが苦手な理由は、人それぞれ異なります。その中には、発達障害などの特性が関係する場合もあります。たとえば、ADHD(注意欠如・多動性障害)の特性を持つ方は、注意を持続するのが難しかったり、計画的に行動するのが苦手だったりするため、片付けが負担に感じられることがあります。こうした特性は決して「できない」と断じられるものではなく、むしろ自分に合った工夫や環境づくりを行うことで、少しずつ改善が見込める場合もあります。専門家に相談しながら、自分のペースで取り組むことが大切です。
この文章では、片付けが苦手な方が抱えるさまざまな要因に焦点を当てています。それぞれの状況に合った方法を見つけ、小さな一歩を踏み出すヒントやきっかけとなる情報をお届けできれば幸いです。
片付けられない理由
ここまで片付けが苦手な人の特徴をまとめてきましたが、今回は片付けができない理由について説明します。
片付ける方法がわからない
片付けが苦手な人の多くは、実は「片付けの方法」を知らないことが理由となっています。片付けはセンスではなく理論(ロジック)に基づいたスキルであり、誰でも練習次第で身につけることができます。しかし、どこから手をつければよいのか分からず、闇雲に取り組むと余計に散らかってしまい、挫折しやすいのが現実です。
片付けが習慣化されていない
片付けが苦手な理由の一つとして、「片付けが習慣化されていない」ことが挙げられます。例えば、物を使った後に元の場所に戻すという基本的な行動が自然にできる人もいれば、それが意識的な努力を必要とする人もいます。特に、物の定位置が決まっていない場合、しまうべき場所を探すのが億劫になり、結果的に物が散らかったままになることがあります。片付けを日々のルーチンとして組み込むことができれば、自然と綺麗な状態が保たれます。この「習慣化」が難しく、片付けを後回しにしてしまう人が多いのです。
時間的、体力的に余裕がない
忙しい日々を過ごしていると、片付けに充てる時間や体力がどうしても不足しがちです。仕事や家庭の用事に追われていると、片付けをしようと思っても後回しになりやすく、物が溜まっていく一方になってしまいます。また、体力的に疲れている状態では、片付けがさらに負担に感じられることでしょう。この「時間や体力の余裕がない」という理由は、現代社会の生活習慣やライフスタイルとも関連しており、多くの人が直面している課題の一つです。それでも、限られた時間の中で少しずつでも片付けを進める方法を模索することが、効果的な整理収納への第一歩となります。
手軽に始められる!効果的な片付け方法

ここでは、手軽に始められる片付け方法について、4つのステップに分けて説明します。
STEP1: 片付ける場所を選ぶ
片付けが苦手な人は、最初にどこを片付けるか迷ってしまうことが多いです。そんなときには、片付け範囲を小さく設定するのがポイントです。例えば、「リビング全体」ではなく「リビングのテーブル」や「引き出し1つ」など、具体的で取り掛かりやすい範囲を選びましょう。また、キッチンの棚や靴箱など、小さく区切られたスペースから始めると進めやすくなります。選んだ場所を決めたら、そこだけに集中することで効率よく片付けを進められます。
STEP2: 持ち物を全て取り出す
片付けるスペースが決まったら、まず全ての物をその場所から取り出しましょう。この工程は、自分がどれだけ物を持っているのかを把握する大切なステップです。「何があるのか分からない」のは片付けが進まない理由の一つですので、すべて目に見える状態にすることで整理収納の第一歩を踏み出せます。この際、物を一時的に広げられるスペースを確保しておくと、作業がスムーズに進みます。
STEP3: 「いるもの」「いらないもの」に分ける
次に「いるもの」と「いらないもの」に分ける作業を行います。ここでは深く考えすぎず、直感で選ぶことが重要です。日常的に使っているものや、大切な思い出があるものを「いるもの」として選びます。一方で、長い間使っていない物や類似するアイテムが複数ある場合は「いらないもの」と判断しましょう。「もったいない」という気持ちが出てくることもありますが、本当に必要なものだけを残すことで、片付け後のすっきりとした部屋を作ることができます。
STEP4: 「いるもの」だけ収納する
最後に、先ほど仕分けた「いるもの」を収納していきます。ここで大切なのは、物の定位置を決めることです。同じカテゴリーの物をまとめて収納することで、探し物を減らし、片付いた状態を保ちやすくなります。また、使用頻度に応じた収納場所を選ぶのも重要です。よく使うものは取り出しやすい手前や目線の高さに、シーズンオフの物やあまり使わない物は奥や上部に収納することで、ストレスなく物を取り出すことができます。
片づけをする際のコツ
時間を決めて行う
片付けを進める際には、事前に時間を決めて行うことが効果的です。ダラダラと時間をかけると集中力が落ち、逆に効率が悪くなることがあります。例えば「15分だけ片付ける」といった短時間の目標を設定することで、片付けに集中しやすくなり、作業を継続しやすくなります。この方法なら、時間的な制約があっても少しずつ整理収納が進みます。
ものの定位置を決める
片付けた後に散らかる原因の一つは、物の定位置が決まっていないことです。片付けを終えた段階で、すべての物に「ここに戻す」というルールを作りましょう。「戻す場所」を決めておけば、物が迷子になることを防ぐだけでなく、探す手間も減って暮らしがぐっと楽になります。特に使用頻度の高い物は、取り出しやすい場所に収納することを意識しましょう。
捨てる判断は急がない
片付けを進める中で、「もったいない」と感じて物を手放せないことはよくある悩みです。その場合、捨てる判断を急ぐ必要はありません。一旦「保留ボックス」に入れておき、一定期間が経過した後に本当に必要かどうかを再度考える方法を取り入れるとよいでしょう。このようにすることで、焦りや罪悪感を感じずに片付けを進められます。
片付いた部屋を保つには…?

見えない収納/見える収納の使い分けをする
部屋をいつでもキレイな状態に保つためには、「見えない収納」と「見える収納」を適切に使い分けることが大切です。見えない収納とは、引き出しや戸棚など内部に物を隠して収納する方法です。部屋がすっきりと見える効果があり、特に来客時や急な片付けに役立ちます。一方で、よく使う物や生活動線上にある物を「見える収納」にすることで、使いやすさや片付けやすさが向上します。両方の利点を組み合わせることで、無理なく整理収納を続けられる環境を作ることができます。
使いやすい収納スペースを作り出す
片付けが苦手な人ほど、収納スペースの使いやすさが整理整頓を続ける鍵となります。使いやすい収納とは、頻繁に使う物が取り出しやすい場所にあることを指します。また、物をカテゴリーごとに分類し、それぞれに専用の収納エリアを設けることが効果的です。例えば、キッチンでは調理器具や食器を用途別に分け、リビングではリモコンや雑誌などをまとめて置ける収納ボックスを活用します。こうした配置を意識すれば、自然と物を元の場所に戻す癖がつき、片付けが楽になります。
生活動線を意識したレイアウトを作る
キレイな状態を保つためには、生活動線を意識した部屋のレイアウトが重要です。生活動線とは、普段の生活で自然に動くルートを指し、家族の人数やライフスタイルによって異なります。この動線上に必要な物を配置することで片付けの手間を減らせます。例えば、玄関には靴やカバンの定位置を設定し、キッチンでは調理器具を作業スペースの近くにまとめるといった方法が挙げられます。これにより物を片付けたり取り出したりする時間が短縮され、整理整頓が習慣化しやすくなります。
正しい片付け方法を知って、快適な生活を送ろう!
本記事では、片付けられない理由や特徴を分析し、簡単かつ効果的な片付け方法をステップごとにご紹介しました。重要なのは、完璧を目指すのではなく、小さな範囲から無理なく始めることです。また、片付けを習慣化し、「いるもの」と「いらないもの」を見極めるスキルを身に付けることで、整頓された部屋を保つことができます。
とはいえ、忙しい毎日の中で片付けを始めるのは、なかなかハードルが高いもの。そんな時は、家事代行サービスや整理収納のプロに頼ってみるのも一つの方法です。家事代行サニーメイドサービスでは、「お片付け・整理収納サービス」をご提供しています。経験豊富なスタッフが、一人ひとりの暮らしに合わせた無理のない整理収納をサポート。「どこから手をつければいいかわからない…」そんなお悩みも、プロの手でスムーズに解決へ。まずは、日々の生活が整っていく心地よさを体感してみませんか?