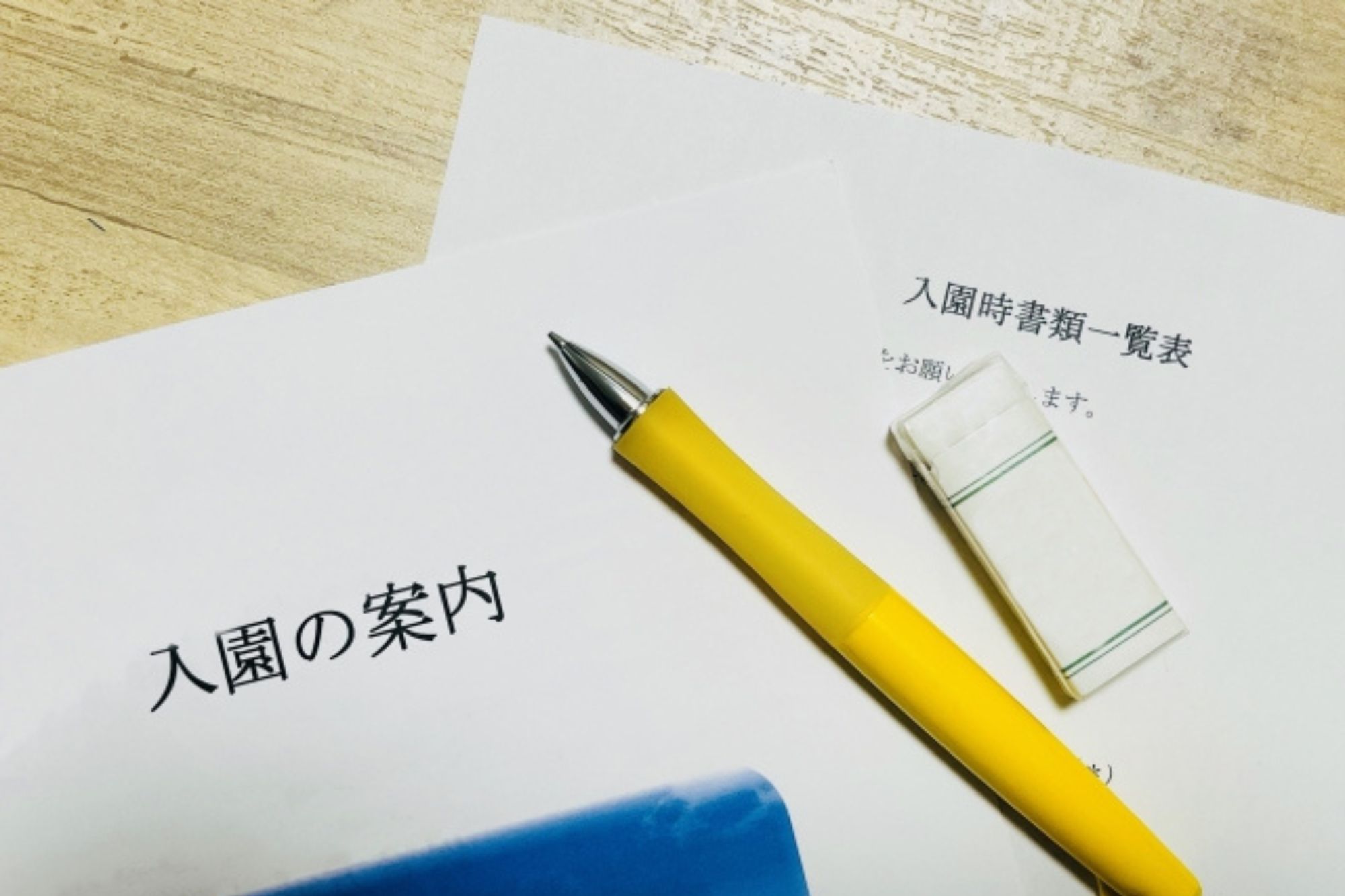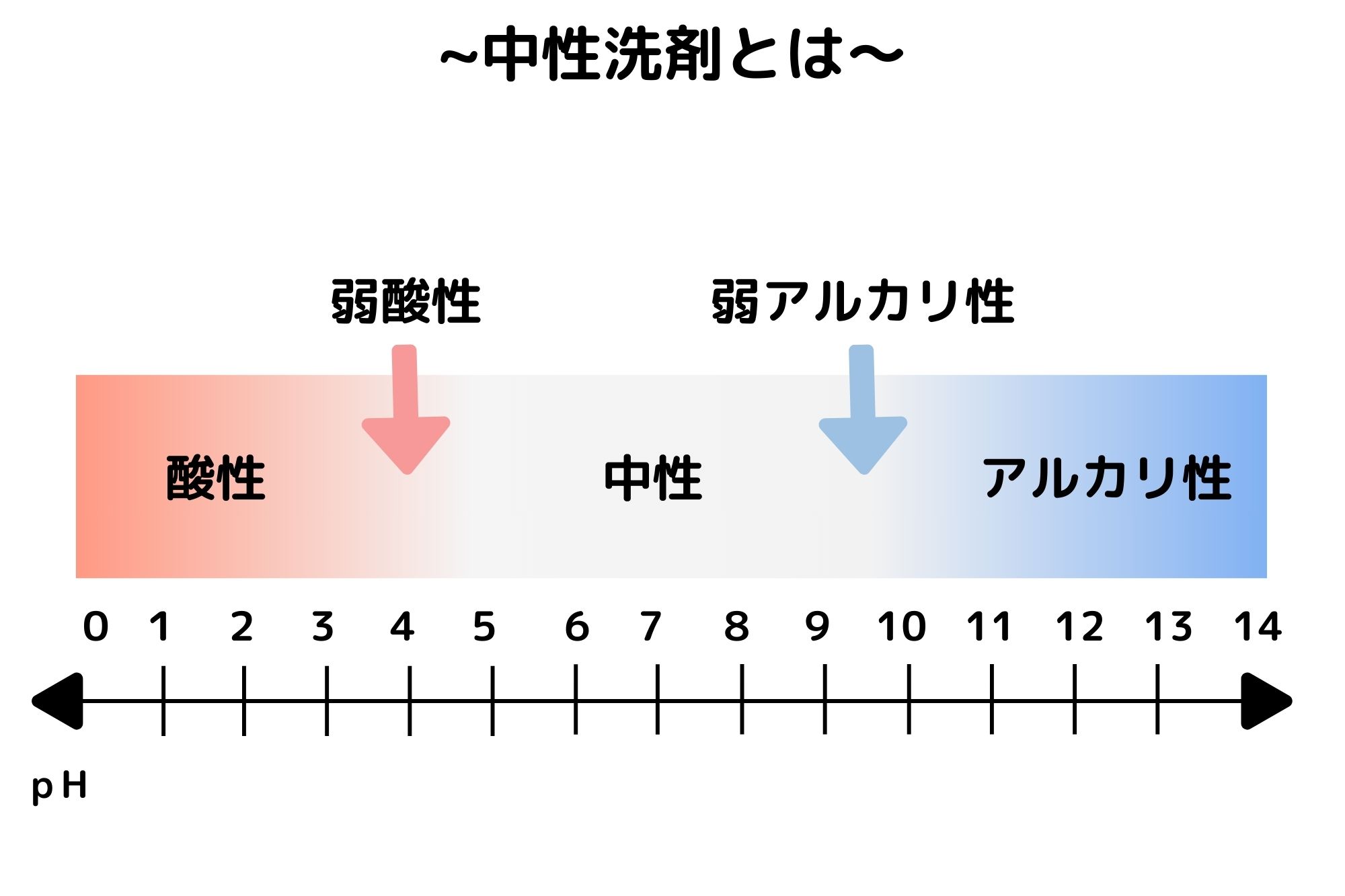COLUMN
コラム
共働き家庭必見!保育園スタートで増える負担を解消する方法
2025.01.29
子どもが保育園に入る時期は、ご家庭にとって大きな節目のひとつです。特に共働き夫婦にとっては、育休復帰を見据えた保育園生活の準備が非常に重要です。共働き夫婦が保育園生活をスムーズにスタートするためのポイントについてご紹介します。
目次
保育園に入る前の準備の重要性

子どもが初めて保育園に通い始めるご家庭では、入園前の準備やご自身の職場復帰に向けた準備など、やるべきことがたくさんあり大変だと思います。また、職場復帰した後には朝の支度や保育園の送り迎え、持ち物の準備など細かいタスクが待っています。それらに加え、仕事や日々の家事もこなさなければならず、日々の負担は一気に増えてしまいます。
このような日々の負担を軽減するためには、夫婦間での家事育児の分担が欠かせません。事前に夫婦間でそれぞれの役割分担について話し合っておくことも、入園前の準備の一環として大切です。
この記事では、共働き夫婦の皆さんが安心して保育園生活をスタートできるように、家事育児の分担のポイントについてご紹介します。
保育園生活スタートで増える家庭の負担
保育園生活が始まることで増える育児の負担について、具体的にどのようなものがあるのか確認していきましょう。
毎日の登園ルーティン
保育園生活がスタートすると、共働き家庭では新たなルーティンが求められます。特に朝は、子どもの着替え、朝食、持ち物の準備、連絡帳の記入など、やるべきことが山積みです。これらをスムーズに進めるには、計画的な時間管理が重要です。準備を怠ると、大きなストレスを抱えることになりかねません。
また、保育園への送り迎えも夫婦の協力が重要です。特に育休復帰後、時間的な余裕がなくなるワーママにとっては、これらのタスクを効率よくこなすための習慣づくりが欠かせません。
仕事と育児の両立における心身のストレス
保育園生活が始まったことで生じるストレスは、単なるタスクの量だけに留まりません。例えば、急な子どもの体調不良による欠勤や、仕事の納期のプレッシャーが続く中での育児対応といった場面も大きな負担になります。特に共働き夫婦の場合、家事や育児の負担に偏りが生じやすく、多くのご家庭で「自分ばかりが担当している」という思いから摩擦が生じることも少なくありません。この不満の背景には、家事や育児のタスクが見えにくいことや、役割が曖昧なまま進んでいることがあります。
上手に分担するためのポイント

実際にどのように家事や育児を分担すれば良いのか、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。ここでは、上手に分担するためのポイントをいくつかご紹介します。
家事・育児の「見える化」をする
共働き夫婦が家事分担をうまく進めるためには、まず「見える化」を行うことが重要です。家事や育児を日々こなしていると、どの作業がどれくらいの負担になっているのか、つい曖昧になりがちです。特に、職場復帰や保育園生活の開始など、家庭の負担が増える兆しがある場合には、改めて細かいタスクの洗い出しを行うと良いでしょう。具体的には、「子どもたちの朝の準備」という大きなカテゴリーを、さらに「着替え」「荷物の準備」「連絡帳の記入」といった形で細分化し、リスト化します。そうすることで家事育児の偏りをリストで確認でき、分担を見直すきっかけになります。
この「見える化」を行う際には、タスク共有管理アプリを使うことをおすすめします。最近は仕事で活用されている方も多いと思いますが、分担したお互いのタスクの状況や変更などをタイムリーに確認することができます。日々の慌ただしい生活の中で共有する時間がなかったり、共有しようと思っていたのに忘れてしまったりすることも、それぞれのタイミングで共有できます。また、共有するという点では、保育園の掲示物やお便りの写真を撮って共有したり、保育園のイベントなどをカレンダーアプリで共有したりすることもできます。それぞれの用途に合ったアプリを駆使することで、日々の家事や育児が「見える」形になり、お互いの負担が軽減されるはずです。
お互いの意見を取り入れて柔軟に分担する
家庭内の役割分担を決める際には、夫婦それぞれの得意な分野やキャパシティに基づいて分担することがポイントです。例えば、パパは子どもと遊ぶことが得意で、ママは「料理」や「片付け」が得意な場合、こうした得意分野を尊重しながら役割を決めると、お互いがストレスを感じにくくなります。また、「ストレスを伴う作業」を片方に偏らせないようにする工夫も重要です。例えば、保育園の送り迎えをいずれか1人が全て担うのではなく、曜日ごとに分担する、相手が担当する日は朝の準備をサポートするといった柔軟なルール設定が有効です。これにより、仕事と育児を無理なく両立させられる環境を作ることができます。
コミュニケーションを重要視する
役割分担を決めるためには、夫婦間での「コミュニケーション」が欠かせません。特に共働き家庭では、仕事や育児の疲れから話し合いを後回しにしがちです。しかし、家事や育児の分担が曖昧なままでは、不満やストレスが溜まる原因になります。一度決めた分担も、生活環境や保育園生活の状況によって変わる可能性があるため、定期的な話し合いを行うことを心掛けましょう。
その他の入園前に決めておいた方がいいこと
① 緊急連絡先の順番
入園に際して、何かあった場合の連絡先として「緊急連絡先」を提出する保育園が多いと思います。基本的に複数の連絡先を提出できるため、「必ず連絡のつく人/すぐにお迎えに行ける人」を1番目とするのが良いでしょう。また、近くに祖父母など親戚が住んでいて協力をお願いできる場合は、事前に調整し緊急連絡先に入れておくことで、緊急時に柔軟な対応ができる可能性もあります。
② ケガや病気になった際の対応
子どものケガや病気などは予測がつかず、いつ保育園から保護者に呼び出しの連絡が入るかわかりません。そのような緊急時にも、慌てることなく素早く子どもを迎えに行けるよう、誰が迎えに行くのか、どこの医療機関を受診するのか、といったことを事前にきちんと相談して決めておきましょう。
家事分担を考えるきっかけを子どもと共有する
子どもが家族の一員として役割を理解する重要性
職場復帰や保育園生活のスタート後、共働き家庭では家事や育児を円滑に進めるための工夫が必要です。そのひとつとして、子どもに家族の一員としての役割を理解してもらうことが挙げられます。共働き夫婦として家族みんなが笑顔で過ごすためには、全員が協力することが大切であり、これは子どもにとっても重要な学びの機会になります。小さなタスクでも「自分が家庭に貢献している」という感覚を持てば、子どもたちは成長する中で自然と責任感を育むことができます。また、家庭の役割といった仕組みを親と共有することで、保育園で必要な準備や生活習慣にも適応しやすくなる効果も期待できます。
簡単なタスクを任せることで、早期から責任感を育む
共働きの家庭で家事分担を成功させるポイントの一つは、子どもに適した簡単なタスクを任せることです。年齢に応じて、「テーブルを拭く」「洗濯物をたたむ」「おもちゃを片付ける」などの小さな仕事を頼むことで、子どもは達成感や満足感を味わうことができ、自然と協力する意識が芽生えます。例えば、3歳の子どもには準備の手伝いや靴を並べるなどの取り組みがおすすめです。これにより、共働き家庭が抱える家事の負担が軽減されるだけでなく、子ども自身も家族に貢献する楽しさを学べます。また、復職後も育児に悩むワーママは、子どもとタスクを共有することで余裕を持ち、精神的な負担を軽減できることもメリットの一つです。小さな役割を任せるプロセスの中で、親子間のコミュニケーションが深まり、家庭全体が協力して動く習慣が根付くでしょう。
時短&効率化のための家事テクニック

家事効率を向上させるためには、時短家電や外部サービスの導入がおすすめです。共働き家庭にとって多忙な日常の中で、食洗機やロボット掃除機、乾燥機能付き洗濯機などの便利な家電は家事にかかる時間を減らしてくれます。また、家事代行サービスや食材宅配サービスを活用することで、日々の負担を軽減できます。
家事の時短・効率化については以下の記事も参考にしてみてください。
共働きでも安心!保育園生活の土台を整えよう

保育園生活の準備には、夫婦間、そして家族全体での協力する意識が鍵となります。入園前に家事や育児の分担を見直し、負担をお互いに分け合うことで、職場復帰後のママが過度な負担を抱え込むことなく、安心して保育園生活を迎えることができるでしょう。また、職場復帰後に仕事や生活のスケジュールが変わることもあります。定期的に分担の見直しをする時間を設けて、無理なく取り組める方法を一緒に考え、実践していくとお互いのストレスや不満も溜まりにくくなるでしょう。
保育園生活は、子どもにとっても、保護者にとっても、新たなスタートとなります。この記事が少しでも皆さんの助けになれば幸いです。お子さんとともに、笑顔あふれる毎日を過ごしてください。